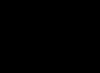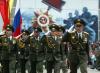コースワーク
酵素反応の速度論
導入
あらゆる生物の生命活動の基礎は化学プロセスです。 生体内のほとんどすべての反応は、天然の生体触媒である酵素の関与によって起こります。
ベルゼリウスは 1835 年に、生物の反応は彼が「触媒」と呼んだ新しい力のおかげで行われることを初めて示唆しました。 彼はこのアイデアを主に、ジャガイモのジアスターゼが硫酸よりも速くデンプンを加水分解するという実験的観察に基づいています。 キューネはすでに 1878 年に、生物体内で触媒力を持つ物質を酵素と呼んでいました。
酵素作用の反応速度論は、酵素によって触媒される反応速度の化学的性質、基質と酵素の相互作用条件、および環境要因への依存性を研究する酵素学の分野です。 言い換えれば、酵素反応速度論により、酵素触媒作用の速度に影響を与える因子の作用の分子機構の性質を理解することができます。 このセクションは、生化学、物理学、数学などの科学の交差点として設立されました。 酵素反応を数学的に説明する最初の試みは、1898 年にデュクロによって行われました。
実際、酵素の研究に関するこのセクションは、現代、つまり実践医学にとって非常に重要です。 それは薬理学者に、細胞代謝、膨大な数の医薬品、さまざまな毒物(これらは酵素阻害剤)の標的を絞った変化のためのツールを提供します。
この研究の目的は、反応速度のさまざまな要因への依存性、反応速度をどのように制御できるか、および反応速度をどのように決定できるかを検討することです。
1. ミカエリス・メンテン反応速度論
酵素反応の速度論を研究する予備実験では、理論的な予想に反して、反応速度は従来の二次反応の場合と同様に酵素 (E) と基質 (S) の濃度に依存しないことが示されました。命令反応。
ブラウンと彼とは独立して、アンリは最初に、反応中に酵素と基質の複合体が形成されるという仮説を立てました。 この仮定は、次の 3 つの実験事実によって確認されました。
a) パパインはフィブリンと不溶性化合物を形成しました (Wurtz、1880)。
b) インベルターゼの基質であるスクロースは酵素を熱変性から保護することができた (O" Sullivan and Thompson, 1890)。
c) 酵素は立体化学的に特異的な触媒であることが示された (Fisher、1898-1899)。
![]()
彼らは最大速度の概念を導入し、次のことを示しました。 飽和曲線(つまり、反応速度の基質濃度への依存性)は等辺双曲線です。 彼らは、観測された最大速度は曲線への漸近線の 1 つであり、セグメントは 2 番目の漸近線によって x 軸上 (負の値の領域) で切り取られることを証明しました。 速度方程式における定数で、最大速度の半分を達成するのに必要な基質濃度と絶対値が等しい。
Michaelis と Menten は、反応速度は ES 複合体の崩壊によって決定されることを示唆しました。 定数 k 2 . これは k 2 の場合にのみ可能です - 最小の速度定数。 この場合、酵素-基質複合体、遊離酵素および基質の間の平衡は、反応速度に比べて急速に確立されます(急速に確立された平衡)。
初期反応速度は次の式で表すことができます。
v = k 2
酵素-基質複合体の解離定数は次のように等しいため、
KS = [E] [S] / = k -1 /k 1
遊離酵素の濃度は次のように表すことができます。
[E] =K S / [S]
反応混合物中の総酵素濃度は次の式で求められます。
[E] t = [E] + [ES] = KS [ES] / [S] + [ES]
基質濃度が十分に高く、すべての酵素分子が ES 複合体の形で存在する (基質が無限に大過剰) 場合、反応は最大速度に達します。 理論的に可能な最大速度に対する初速度の比は、[ES] と [E] t の比に等しくなります。
v / V max = / [E] t = / (KS / [S] + ) = 1 / (KS + [S] +1)

これは古典的な方程式です ミカエリスそして メンテン、これは 1913 年に出版されて以来、数十年にわたってすべての酵素速度論研究の基本原則となり、いくつかの制限はあるものの、今日に至るまでそのままです。
元のミカエリス・メンテン方程式にはいくつかの制限があることが後に判明しました。 それは公平です、つまり 以下の制限条件がすべて満たされる場合にのみ、特定の酵素によって触媒される反応の速度論を正確に記述します。
)速度論的に安定した酵素-基質複合体が形成される。
) 定数 K S は酵素-基質複合体の解離定数です。これは の場合にのみ当てはまります。
) 基質濃度は反応中に変化しません。つまり、 遊離基質の濃度はその初期濃度に等しい。
) 反応生成物は酵素からすぐに分離されます。 速度論的に有意な量の ES 複合体は形成されません。
) 反応の第 2 段階は不可逆的です。 より正確には、(実際に生成物が存在しないことによる)逆反応が依然として無視できる場合には、初速度のみを考慮します。
)酵素の各活性部位に結合する基質分子は 1 つだけです。
) すべての反応物について、活性の代わりにその濃度を使用できます。
ミカエリス・メンテン方程式は、酵素作用の定量的記述の出発点として機能します。 ほとんどの酵素の反応速度論的挙動は、ミカエリス-メンテン方程式の基礎となる理想化されたスキームによって暗示されるものよりもはるかに複雑であることを強調しておく必要があります。 この方程式の導出では、酵素-基質複合体が 1 つだけ存在することを前提としています。 一方、実際には、ほとんどの酵素反応では、このような複合体が少なくとも 2 つまたは 3 つ形成され、特定の順序で発生します。
ここで、EZ は真の遷移状態に対応する複合体を示し、EP は酵素と反応生成物の間の複合体を示します。 また、ほとんどの酵素反応には複数の基質が関与しており、したがって 2 つ以上の生成物が形成されることも指摘できます。 2 つの基質 S 1 および S 2 との反応では、3 つの酵素-基質複合体、つまり ES 1、ES 2、および ES 1 S 2 が形成されます。 反応により2つの生成物P 1 およびP 2 が生成される場合、少なくとも3つの追加の錯体EP 1 、EP 2 およびEP 1 P 2 が存在する可能性がある。 このような反応には多くの中間段階があり、それぞれが独自の速度定数によって特徴付けられます。 2 つ以上の反応物が関与する酵素反応の速度論的分析は非常に複雑な場合が多く、電子コンピューターの使用が必要です。 ただし、すべての酵素反応の反応速度論を分析する場合、出発点は常に上記のミカエリス-メンテン方程式です。
1.1 定数の性質K方程式の中で
酵素反応速度論の方程式
2 番目の公準は、定数 K S が 式中の は、酵素-基質複合体の解離定数です。
ブリッグスとホールダンは 1925 年に、元のミカエリス メンテン方程式が に対してのみ有効であることを証明しました。 初等段階 E+S ES の平衡が次の段階の速度と比較して非常に早く確立されるとき。 したがって、そのような運動機構(初期のミカエリス・メンテン条件に従い、遅い初等段階が 1 つあり、それに対して他のすべての初等段階の平衡はすぐに確立される)は、「高速平衡」の仮定を満たすと言われます。 ただし、k 2 が大きさのオーダーで k -1 に匹敵する場合は、 ,
酵素と基質の複合体の濃度の経時変化は、次の微分方程式で表すことができます。
d / dt = k 1 [E] [S] - k -1 - k 2
初期反応速度を考慮しているため、つまり 逆反応がまだ起こっておらず、定常段階がすでに過ぎているとき、基質が過剰であるため、形成された酵素-基質複合体の量は分解された酵素の量と等しくなります。 (定常原理、またはブリッグスとハルダンの反応速度論、または化学反応速度論のボーデンシュタイン原理)そしてそれは真実です。
d/dt=0
これを微分方程式に代入すると、遊離酵素の濃度の式が得られます。
[E] = (k -1 + k 2) / k 1 [S]
[E] T = [E] + = [(k -1 + k 2) / k -1 [S] + 1] =
= (k -1 + k 2 + k -1 [S]) / k 1 [S]
定常状態の方程式:
K 1 [S] [E] T / (k -1 + k 2 + k 1 [S])
なぜなら v = k 2 であれば、次のようになります。
v = k 1 k 2 [S] [E] T / (k -1 + k 2 + k 1 [S]) = k 2 [S] [E] T / [(k -1 + k 2) / k 1+[S]]
この場合
V max = k 2 [E] T
ミカエリス・メンテン方程式から得られる最大速度に等しくなります。 ただし、ミカエリス・メンテン方程式の分母の定数は K S ではありません。 ,
それらの。 酵素と基質の複合体の解離定数ではなく、いわゆる ミカエリス定数:
K m = (k -1 + k 2) / k 1
K m は、 の場合にのみ K S に等しくなります。
速度方程式の分母が定数の場合は、次の式で表されます。
K k = k 2 / k 1
ヴァン・スライクによれば、こう呼ばれています。 運動定数。
定常状態方程式は、d / dt = 0 を仮定せずに微分方程式から取得することもできます。値 [E] = [E] T - を微分方程式に代入すると、変換後に次の結果が得られます。
= (k 1 [S] [E] T - d / dt) / (k 1 [S] + k -1 + k 2)
この式から定常状態方程式を得るには、d / dt = 0 である必要はありません。不等式 d / dt が満たされていれば十分です。<< k 1 [S] [E] T . Этим объясняется, почему можно достичь хорошего приближения в течение длительного времени при использовании принципа стационарности.
微分定常状態方程式は次のとおりです。
d / dt = T / (k 1 [S] + k -1 + k 2) 2 ] (d [S] / dt)
この式は明らかに 0 ではありません。
1.2 ミカエリス・メンテン方程式の変換
元のミカエリス・メンテン方程式は双曲線方程式であり、定数の 1 つ (V max) が曲線の漸近線です。 もう 1 つの定数 (K m) は、負の値が 2 番目の漸近線によって決定され、V max / 2 を達成するのに必要な基質濃度に等しくなります。これは検証が簡単です。
v=V max / 2、すると
V max / 2 = V max [S] / (K m + [S])
V max / V max = 1 = 2 [S] / (K m + [S]) m + [S] = 2 [S]、つまり [S] = K m at v = V max /2。
ミカエリス・メンテン方程式は、実験データをグラフで表現するのに便利な他の形式に代数的に変換できます。 最も一般的な変換の 1 つは、単純に、方程式の左辺と右辺の逆数を互いに等しくすることになります。


変換の結果、次の式が得られます。

と呼ばれるもの ラインウィーバー・バーク方程式。 この式によれば、座標 1/[S] および 1/v にプロットされたグラフは直線であり、その傾きは K m /V max に等しく、縦軸で切り取られたセグメントは 1/ に等しくなります。 V最大 二重逆数法を使用して作成されたこのようなグラフには、V max をより正確に決定できるという利点があります。 座標 [S] および v でプロットされた曲線では、V max は漸近値であり、決定される精度ははるかに低くなります。 Lineweaver-Burk グラフの X 軸で切り取られたセグメントは、-1/K m に等しくなります。 酵素阻害に関する貴重な情報もこのグラフから収集できます。
ミカエリス・メンテン方程式のもう 1 つの変換は、ラインウィーバー・バーク方程式の両辺に V max *v を掛け、いくつかの追加の変換を行った後、次のようになります。

座標 v および v/[S] の対応するグラフは次のように表されます。 e 4、図。 1]。 こんなスケジュールです( イーディ・ホフスティーチャート) を使用すると、V max と K m の値を非常に簡単に決定できるだけでなく、Lineweaver-Burk プロットでは検出されない、線形性からの逸脱の可能性を特定することもできます。
この方程式は別の形式で線形化することもできます
[S] / v = K m / V max + [S] / V max
この場合、[S] に対する [S] / v の依存性をプロットする必要があります。 結果として得られる直線の傾きは 1/V max です。 縦軸と横軸で切り取られたセグメントは、それぞれ (K m / V max) と (-K m) に等しくなります。 このグラフは作成者の名前にちなんで呼ばれます。 ヘインズチャート.
統計分析により、Edie-Hofstee 法と Haynes 法は Lineweaver-Burk 法よりも正確な結果が得られることが示されました。 その理由は、イーディー ホフスティー グラフとヘインズ グラフでは、両方の座標軸にプロットされた量に従属変数と独立変数の両方が含まれるためです。
1.3 反応速度論に対する基質濃度の影響
多くの場合、基質濃度が一定という条件が満たされません。 一方で、基質の酵素活性の阻害が頻繁に発生するため、一部の酵素とのインビトロ反応では過剰な基質は使用されません。 この場合、その最適濃度のみを使用することができ、これは、上で論じた機構の動力学方程式を満たすのに必要な過剰な基質を常に提供するとは限らない。 さらに、生体内細胞では、この状態を達成するために必要な過剰な基質は通常は達成されません。
基質が過剰ではないため、反応中に基質の濃度が変化する酵素反応では、酵素 - 基質複合体の解離定数は次のようになります。
KS = ([S] 0 - - [P]) [E] T - )/
([S] 0 - t = 0 での基質濃度)。 この場合、初期反応速度 (定常状態) は次の式で求められます。
v= V max / (K m + )
ここで、 は一度に使用する基質の濃度です。
ただし、 [S] o = の場合、次の 2 つの場合の近似解を書くことができます。
) t の値が大きいためにこの不等式が成り立つ場合、つまり 反応中に初期基質濃度の 5% 以上が消費された場合。
) 酵素濃度が基質濃度と比較して無視できない場合、したがって酵素-基質複合体の濃度を考慮する必要があります。
t が大きく、濃度が [S]0 に比べて無視できる場合、酵素 - 基質複合体の解離定数の方程式は次のようになります。
KS = ([S] 0 - [P]) ([E] T - ) /
反応中に変化する濃度値は、([S] 0 + )/2 の値で十分に近似できます。 = [S] 0 - [P] なので、平均速度。 次のように表現できます
![]()
この式と近似値を代入すると、
v= V max / (K m + )、
我々が得る:
この近似から計算された値を、正確な統合されたミカエリス・メンテン方程式から得られた値と比較すると、K m の決定における誤差が判明します。 基質の 30% と 50% を消費した場合、それぞれ 1 % と 4% になります。 したがって、この近似における誤差は、測定誤差に比べて無視できる程度です。
基質の消費量が初期濃度の 5% を超えないが、酵素濃度が [S] と比較して無視できないほど高い場合、酵素 - 基質複合体の解離定数は次のようになります。
K s = ([S] 0 - ) ([E] T - ) /
彼の解決策は比較的
考えられる 2 つの解のうち、負の解のみを選択できます。これは、初期条件 = 0 ([S] 0 = 0 または [E] T = 0) のみを満たすためです。 v/V 比の方程式から類推して、 max、初速度の方程式が得られました。 先ほどの酵素-基質複合体の解離定数の方程式から、式 v = k 2 および V max = k 2 [E] T を使用して得られる二次方程式は、次の形式に簡略化できます。
[S] 0 V max / v = K s V max / (V max - v) + [E] T
考慮すべき 2 つの限定的なケースがあります。 最初の場合 [S]<
v = (V max / K m) [S] = k[S]
したがって、見かけの一次反応と、見かけの一次反応速度定数であるk=V max /K m が得られた。 その実際の次元は時間 -1 ですが、これはいくつかの基本段階の 1 次および 2 次の速度定数の組み合わせです。 k 1 k 2 [E] T /(k -1 + k 2) . 見かけ上の一次条件下で k 反応の進行度の尺度です。
別の極端なケース: [S] >>
キロ。
ここで定数 K m
は [S] に比べて無視できるため、v = V max が得られます。
1.4 速度論的に安定した酵素-生成物複合体の形成
反応中に速度論的に安定した酵素と生成物の複合体が形成される場合、反応メカニズムは次のようになります。
定常状態の仮定を使用すると、次の微分方程式を書くことができます。
d /dt = k 1 [E] [S] + k -2 - (k -1 + k 2) = 0 /dt = k 2 - (k -2 + k 3) = 0
これらの方程式から、次のことがわかります。
= [(k -2 + k 3) / k 2 ]
[E] = [(k -1 k -2 + k -1 k -3 + k 2 k 3) / k 1 k 2 [S]]
v = k 3 なので
および [E] T = [E] + + =
= [(k -1 k -2 + k -1 k -3 + k 2 k 3) / k 1 k 2 [S] + (k -2 + k 3) / k 2 + 1] =
= ( (k -2 + k 3) + k 1 k 2 [S]] / k 1 k 2 [S])
我々が得る
K 1 k 2 [S] [E] T / (k -2 + k 3 + k 2)]= k 1 k 2 k 3 [S] [E] T / (k -2 + k 3 + k 2) ] =
= [E] T [S] / [(k -1 k -2 + k -1 k -3 + k 2 k 3) / k 1 (k -2 + k 3 + k 2) + [S]]
あれは
V max = [E] Tm = (k -1 k -2 + k -1 k -3 + k 2 k 3) / k 1 (k -2 + k 3 + k 2)
この場合、直接測定できるのは比率のみであるため、個々の速度定数の具体的な値を計算することはすでに非常に困難です。 酵素反応のメカニズムがより複雑になると、反応に 3 つ以上の錯体が関与する場合、状況はさらに複雑になります。これは、方程式内の速度定数の数が当然はるかに多くなり、それらの関係もより複雑になるためです。
しかし、最初の複合体形成の可逆反応の後、その後の基本段階が不可逆的である場合、状況は単純化されます。 この機構に従う酵素の重要な代表は、タンパク質分解酵素とエステラーゼです。 それらの反応のメカニズムは次のように書くことができます。
ここで、ES` は水にさらされると分解するアシル酵素中間体です。 我々は書ける
V max = k 2 k 3 [E] 0 / (k 2 + k 3) = k cat [E] 0m = k 3 (k -1 + k 2) / (k 2 + k 3) k 1 cat / K m = k 2 k 1 / (k -1 + k 2) = k 2 / K m '
アシル化段階のミカエリス定数は、K m -K s である。k cat /K m の比が高くなるほど、基質の特異性が高くなる。
水と競合できる求核剤 (N) の存在下で実験を実行すると、定数の決定が大幅に簡素化されます。 それから

k 3 = k 3 ’と P i (i = 1, 2, 3) は積です。
v i = k cat, i [S] / (K m + [S]) cat, 1 = k 2 (k 3 + k 4 [N]) / (k 2 + k 3 + k 4 [N]) cat, 2 = k 2 k 3 / (k 2 + k 3 + k 4 [N]) cat、3 = k 2 k 4 [N] / (k 2 + k 3 + k 4 [N]) m = K s ( k 3 + k 4 [N]) / (k 2 + k 3 + k 4 [N])
/v N = K s (k 3 + k 4 [N]) / k 2 k 3 [S] + (k 2 + k 3 + k 4 [N]) / k 2 k 3
K s / k 2 = K m / k cat であることが知られており、求核剤が存在しない場合は、
1/v = K s / k 2 [S] + (k 2 + k 3) / k 2 k 3
定数を決定するには、座標 1/v N (および 1/v) - 1/[S] の線の交点を使用できます。 二重逆座標の 2 本の直線が第 2 象限で交差します。 求核試薬が存在しない場合、直線と縦軸との交点は1/V max および1/k cat として定義され、横軸との交点は-1/K m として定義される。 2 本の線の交点の座標: -1/K s と 1/k 3。 1/V max と 1/k 3 の間の距離は 1/k 2 です。
1.5 完全な反応速度曲線の分析
ミカエリス・メンテン方程式は、元の形式では不可逆反応にのみ適用されます。 初速度のみを考慮し、生成物の量が不足して逆反応が起こらず、反応速度に影響を与えない反応まで。 不可逆反応の場合、完全な反応速度曲線を簡単に解析できます(任意の時間間隔 t ),
元のミカエリス・メンテン方程式を統合します。 したがって、この場合、反応中に中間酵素基質複合体が 1 つだけ形成されるという仮定が残ります。 時間間隔 t なので、
制限はありません。分析時の基質の濃度は、最初に導入された濃度と同じであってはなりません。 したがって、反応中の[S]の変化も考慮する必要があります。 S 0 を基質の初期濃度とします (S 0 - y )
- 時間 t における濃度 .
次に、元のミカエリス - メンテン方程式に基づいて (y の場合)
- 変換された基質の量)、次のように書くことができます。
dy / dt = V max (S 0 - y) / (K m +S 0 - y)
逆数をとり、変数を除算して、y にわたって積分します。
0からyまでの範囲
(V max は次のように指定されます) V):
(2.303 / t) log = V / K m - (1 / K m) (y / t)
したがって、方程式の左辺の y/t (フォスター ニーマン座標) への依存性をプロットすると、 ,
傾きのある直線が得られます (-1/K m) ,
縦軸のセグメントを切り取る(V/K m) ,
X 軸はセグメント V です。積分方程式は別の方法でも線形化できます。
t / 2.3031 lg = y / 2.303 V lg + K m / V
または t/y = 2.3031 K m lg / V y +1/V
可逆反応を研究している場合、どのような時間間隔を扱っているかに注意を払う必要があります。 酵素と基質を混合した瞬間に、いわゆる前定常期が始まり、数マイクロ秒またはミリ秒続きます。その間、定常状態に対応する酵素-基質複合体が形成されます。 かなり長期間にわたる可逆反応を研究する場合、この段階では反応がどの方向にも全速力で進行しないため、この段階は重要な役割を果たしません。
左から右に進行する反応の場合、反応に参加する酵素-基質複合体は前定常期の終わりにのみ律速濃度に達します。 準定常状態, 律速酵素-基質複合体の濃度が定常状態の最大濃度値に近づく状態は、10分の数秒または1秒続きます。 この段階では、生成物の形成 (または基質の消費) 速度は時間の経過とともにほぼ直線的になります。 理論的には、生成物の形成はまだ起こっていませんが、実際にはその濃度が非常に低いため、逆反応の速度は正反応の速度に影響を与えません。 この直線相は初期反応速度と呼ばれますが、これまではそれのみを考慮してきました。
次の段階の右から左への反応も、生成物の濃度が徐々に増加するため加速されます。 (遷移状態;以前に観察された時間の直線性は失われます)。 この段階は、左から右への反応速度が右から左への反応速度と等しくなるまで続きます。 これは状態です ダイナミックバランス、反応は両方向に同じ速度で継続的に続くためです。
2. 酵素反応速度を左右する要因
.1 酵素反応速度の温度依存性
環境の温度が上昇すると、酵素反応の速度が増加し、ある最適温度で最大値に達し、その後ゼロに低下します。 化学反応では、温度が10℃上がると反応速度が2~3倍になるという法則があります。 酵素反応の場合、この温度係数は低くなります。10℃ごとに、反応速度は 2 倍またはそれ以下に増加します。 その後の反応速度のゼロへの減少は、酵素ブロックの変性を示します。 ほとんどの酵素の最適温度値は 20 ~ 40 ℃の範囲にあります。酵素の熱不安定性はそのタンパク質の構造に関連しています。 一部の酵素は約40℃の温度ですでに変性していますが、それらの主要部分は40~50℃を超える温度で不活化されます。一部の酵素は低温、つまり低温によって不活化されます。 0℃に近い温度では変性が起こります。
体温(発熱)の上昇により、酵素によって触媒される生化学反応が促進されます。 体温が 1 度上昇するごとに、反応率が約 20% 増加することは簡単に計算できます。 約39〜40℃の高温では、病気の生物の細胞内で内因性基質が無駄に使用されるため、食物を補充する必要があります。 さらに、約 40°C の温度では、一部の非常に熱不安定性の酵素が変性する可能性があり、生化学プロセスの自然な過程が混乱します。
低温は酵素の空間構造のわずかな変化により可逆的な不活性化を引き起こしますが、活性中心と基質分子の適切な構成を破壊するには十分です。
2.2 反応速度の媒体の pH 依存性
ほとんどの酵素には、その活性が最大となる特定の pH 値があります。 この pH 値の上下では、これらの酵素の活性が低下します。 ただし、すべての場合において、酵素活性の pH 依存性を表す曲線が釣鐘型であるわけではありません。 場合によっては、この依存性が直接表現されることもあります。 酵素反応速度の pH 依存性は、主に酵素の活性中心の官能基の状態を示します。 培地のpHの変化は、基質の結合(接触部位)またはその変換(触媒部位)のいずれかに関与する、活性中心のアミノ酸残基の酸性基および塩基性基のイオン化に影響を与えます。 )。 したがって、pH の特定の影響は、酵素に対する基質の親和性の変化、酵素の触媒活性の変化、あるいはその両方の理由によって引き起こされる可能性があります。
ほとんどの基質には酸性基または塩基性基があるため、pH は基質のイオン化の程度に影響します。 酵素は、基質のイオン化または非イオン化のいずれかに優先的に結合します。 明らかに、最適な pH では、活性部位の官能基は最も反応性の高い状態にあり、基質はこれらの酵素基による結合に好ましい形になります。
酵素活性の pH 依存性を表す曲線を作成する場合、多くの酵素の K m 値は pH の変化とともに変化するため、通常、すべての pH 値での測定は酵素が基質で飽和する条件下で実行されます。
酵素活性の pH 依存性を特徴付ける曲線は、酵素が静電気的に中性の基質、または荷電基が触媒作用において重要な役割を果たしていない基質に作用する場合、特に単純な形状になることがあります。 このような酵素の例はパパインおよびインベルターゼであり、これらは中性スクロース分子の加水分解を触媒し、3.0〜7.5のpH範囲で一定の活性を維持します。
最大酵素活性に対応する pH 値は、この酵素の通常の細胞内環境に特徴的な pH 値と必ずしも一致しません。 後者は最適 pH を上回る場合も下回る場合もあります。 これは、酵素活性に対する pH の影響が、細胞内の酵素活性の調節に関与する要因の 1 つである可能性があることを示唆しています。 細胞には何百もの酵素が含まれており、それぞれの酵素が pH の変化に対して異なる反応をするため、細胞内の pH 値はおそらく細胞代謝の複雑な制御システムにおける重要な要素の 1 つです。
2.3 活性による酵素量の測定
) 触媒反応の一般的な化学量論。
)補因子(金属イオンまたは補酵素)が必要になる可能性があります。
) 酵素活性の基質および補因子濃度への依存性、すなわち 基質と補因子の両方の K m 値。
)最大酵素活性に対応するpH値。
) 酵素が安定し、高い活性を維持できる温度範囲。
さらに、基質の消失速度または反応生成物の出現速度を決定できる、かなり単純な分析手法を自由に使用できるようにする必要があります。
可能な限り、酵素アッセイは最適な pH と飽和濃度を超える基質濃度を維持する標準条件下で行われます。 この場合、初速度は基質に関するゼロ次反応に対応し、酵素の濃度にのみ比例します。 補因子(金属イオンまたは補酵素)を必要とする酵素の場合、これらの補因子の濃度も飽和濃度を超える必要があるため、酵素濃度が反応の律速因子となります。 通常、生成物の形成速度の測定は、基質の消失速度の測定よりも高い精度で行うことができます。これは、通常、ゼロ次反応速度を維持するには基質が比較的高濃度で存在する必要があるためです。 反応生成物の生成速度は、化学的または測光的方法によって測定できます。 2 番目の方法は、反応の進行状況をレコーダーに継続的に記録できるため、より便利です。
国際協定によれば、酵素活性の単位は、最適条件下、25℃で1分間に1マイクロモルの基質の変換を引き起こすことができる酵素の量とみなされます。 特定の活動酵素は、タンパク質 1 mg あたりの酵素活性の単位数です。 この値は酵素製剤の純度の基準として使用されます。 酵素が精製されるにつれて増加し、理想的に純粋な調製物の最大値に達します。 下 回転数反応速度が酵素濃度によって制限される条件下で、酵素 1 分子あたり (または活性中心あたり) 単位時間あたりに変換される基質分子の数を理解します。
2.4 酵素の活性化
酵素の調節は、酵素と一般に呼ばれるさまざまな生物学的成分または外来化合物 (たとえば、薬物や毒物) との相互作用を通じて実行されます。 修飾子または規制当局 酵素。酵素に対する修飾子の影響下で、反応は加速されたり(活性化因子)、遅くなったりすることがあります。 (阻害剤)。
酵素の活性化は、修飾因子の作用後に起こる生化学反応の加速によって決まります。 活性化因子の 1 つのグループは、酵素の活性中心の領域に影響を与える物質で構成されます。 これらには、酵素補因子と基質が含まれます。 補因子(金属イオンおよび補酵素)は、複合酵素の必須の構造要素であるだけでなく、本質的にそれらの活性化因子でもあります。
金属イオンは非常に特異的な活性化剤です。 多くの場合、一部の酵素は 1 つではなく、複数の金属のイオンを必要とします。 例えば、細胞膜を越えて一価陽イオンを輸送する Na + 、K + -ATPase の場合、活性化剤としてマグネシウム、ナトリウム、カリウムのイオンが必要です。
金属イオンによる活性化は、さまざまなメカニズムを通じて発生します。 一部の酵素では、それらは触媒部位の一部です。 場合によっては、金属イオンが酵素の活性中心への基質の結合を促進し、一種の架橋を形成します。 多くの場合、金属は酵素ではなく基質と結合して、酵素の作用に好ましい金属基質複合体を形成します。
基質の結合および触媒作用における補酵素の関与の特異性は、酵素反応の活性化を説明します。 補因子の活性化効果は、補因子で飽和していない酵素に作用する場合に特に顕著です。
基質は、特定の濃度制限内では活性化剤でもあります。 基質が飽和濃度に達した後は、酵素活性は増加しません。 基質は酵素の安定性を高め、酵素の活性中心の望ましい立体構造の形成を促進します。
金属イオン、補酵素およびそれらの前駆体および活性類似体、
基質は酵素活性化薬として実際に使用できます。
一部の酵素の活性化は、分子の活性中心に影響を与えない修飾によって実行できます。 この変更にはいくつかのオプションがあります。
1) 非アクティブな先行タスクのアクティブ化 - プロ酵素、または チモーゲン。 たとえば、ペプシノーゲンからペプシンへの変換 ;
2) 酵素分子に特定の修飾基を付加することによる活性化。
3) 不活性タンパク質-活性酵素複合体の解離による活性化。
2.5 酵素阻害
タンパク質の 1 つまたは別の側鎖と多かれ少なかれ特異的に相互作用し、酵素活性の阻害につながる試薬があります。 この現象により、この酵素反応に関与するアミノ酸側残基の性質を研究することが可能になります。 しかし、実際には、多くの微妙な点を考慮する必要があり、特定の阻害剤で得られた結果を明確に解釈することは非常に困難であり、しばしば疑問の余地があります。 まず、阻害剤を使用した反応が、その反応に関与する側鎖の性質を研究するのに適しているためには、次の基準を満たしている必要があります。
) 具体的であること、つまり 阻害剤は目的の基のみをブロックする必要があります。
)酵素活性を阻害し、この阻害は修飾基の数が増加するにつれて完全になるはずです。
) 試薬はタンパク質の非特異的変性を引き起こしてはなりません。
阻害剤には、可逆的と不可逆的な 2 つのグループがあります。 この区分は、透析後または阻害剤による酵素溶液の強力な希釈後の酵素活性の回復の基準に基づいています。
作用機序によれば、競合的、非競合的、非競合的、基質およびアロステリック阻害が区別されます。
競合阻害
競合阻害は、基質類似体によって引き起こされる阻害を研究することによって発見されました。 これは、基質と構造が似ている阻害剤の酵素の活性中心に結合して酵素反応を阻害し、酵素と基質の複合体の形成を妨げることです。 競合阻害では、構造が類似している阻害剤と基質が酵素の活性部位をめぐって競合します。 より大きな分子の化合物は活性中心に関連付けられます。
阻害のメカニズムに関するこのような考えは、競合阻害反応の速度論に関する実験によって確認されました。 したがって、競合阻害の場合、基質類似体はすでに形成された酵素-基質複合体の分解速度に影響を及ぼさないことが示されました。 「無限大」過剰の基質を使用すると、阻害剤の存在下でも非存在下でも同じ最大速度が得られます。 逆に、阻害剤は解離定数とミカエリス定数の値に影響を与えます。 このことから、阻害剤は基質との結合に何らかの形で関与するタンパク質グループと反応するため、これらのグループとの相互作用により、基質結合の強度が低下する(つまり、結合可能な酵素分子の数が減少する)と結論付けることができます。基質への結合が減少します)。
その後、速度論的競合阻害は基質の類似体だけでなく、化学構造が基質の構造と完全に異なる他の試薬によっても引き起こされる可能性があることが示されました。 これらの場合、試薬は基質結合に関与する基と相互作用するとも想定されました。
競合阻害については、理論的には 2 つの可能性が存在します。
1) 酵素の結合中心と触媒中心が重なっている。 阻害剤はそれらに結合しますが、影響を与えるのは結合中心のグループのみです。
2) 酵素分子内の結合中心と触媒中心は空間的に分離されています。 阻害剤は結合部位と相互作用します。

ここで、I は阻害剤、KI は酵素阻害剤複合体の解離定数です。
相対速度(阻害剤の存在下で測定された酵素反応速度の比(v i)) ,
最高速度まで)は次と等しい
v i / V = / [E] T
総酵素濃度についてはそれが真実であるため、
[E] T = [E] + +
1 / v i = (K s / V[S]) (1 + [I] / K I) + 1 / V
明らかに、[I] = K I の場合 , その場合、直線の傾きは、[S] に対する 1/v 0 の依存性の 2 倍になります (v 0 は阻害剤の非存在下での酵素反応の速度です)。
阻害の種類は通常、グラフによって決定されます。 競合阻害は、Lineweaver-Burk プロット (つまり、1/v i 座標のプロット) をプロットすることによって最も簡単に認識できます。 および 1/[S]) を異なる阻害剤濃度で測定します。 真の競合阻害では、傾斜角の正接が異なり、縦軸 (1/v i 軸) と交差する一連の直線が得られます。 一点に。 阻害剤のどの濃度でも、酵素活性が最大になるような高濃度の基質を使用することが可能です。
競合阻害の例は、コハク酸デヒドロゲナーゼの活性に対するさまざまな物質の影響です。 この酵素は、環状酵素システム、クレブス回路の一部です。 その天然基質はコハク酸塩であり、同様の競合阻害剤は同じクレブス回路の中間生成物であるオキサロ酢酸塩です。
コハク酸デヒドロゲナーゼの同様の競合阻害剤はマロン酸であり、生化学研究でよく使用されます。
競合阻害の原理は、多くの薬理学的薬物、農業害虫を駆除するために使用される殺虫剤、および化学兵器の作用の基礎となっています。
例えば、第四級アンモニウム塩基および有機リン化合物の誘導体を含む一群の抗コリンエステラーゼ薬は、基質アセチルコリンに対するコリンエステラーゼ酵素の競合阻害剤です。 コリンエステラーゼは、コリン作動系 (神経筋シナプス、副交感神経系など) のメディエーターであるアセチルコリンの加水分解を触媒します。 抗コリンエステラーゼ物質は、酵素の活性部位をめぐってアセチルコリンと競合し、それに結合して酵素の触媒活性をオフにします。 プロゼリン、フィゾスチグミン、セビンなどの薬剤は酵素を可逆的に阻害し、アルミン、ニブフィン、クロロホス、ソマンなどの有機リン系薬剤は不可逆的に作用して、酵素の触媒基をリン酸化します。 それらの作用の結果として、アセチルコリンは神経興奮の媒介物質であるシナプスに蓄積します。 体は蓄積されたアセチルコリンによって中毒されます。 アセチルコリンが蓄積すればするほど、阻害剤がコリンエステラーゼの活性中心から早く追い出されるため、可逆的阻害剤の効果は徐々に薄れていきます。 不可逆的阻害剤の毒性は比較にならないほど高いため、農業害虫、家庭用昆虫、齧歯動物(クロロホスなど)の防除や、化学兵器(サリン、ソマンなど)として使用されます。
非競合阻害
非競合的阻害では、特定の阻害剤は酵素-基質複合体の解離定数に影響を与えません。 一方、達成可能な最大反応速度は、たとえ基質が無限大に過剰であっても、阻害剤の存在下では、阻害剤の非存在下よりも低くなります。 阻害の存在は、阻害剤がタンパク質に結合していることを証明します。 阻害剤の存在下でも非存在下でも解離定数が不変であることは、基質とは異なり、阻害剤が異なる基に結合することを示しています。 理論的な観点から、このような阻害のメカニズムはさまざまな方法で解釈できます。
a) 酵素の結合中心と触媒中心は異なります。 この場合、触媒中心に関連する阻害剤が酵素の活性を低下させ、達成される最大量が減少します。
酵素と基質の複合体の形成に影響を与えることなく、速度を向上させます。
b) 結合中心と触媒中心は次のように重なっています。
酵素の表面に結合し、阻害剤はタンパク質の他のグループに結合します。 酵素の表面への阻害剤の結合により、タンパク質の情報が変化し、触媒作用にとって不利になります。
c) 阻害剤は触媒部位にも結合部位にも結合せず、タンパク質の立体構造に影響を与えません。 ただし、タンパク質表面の領域上の電荷分布が局所的に変化する可能性があります。 この場合、例えば活性の発現に必須の基のイオン化が不可能になった場合、または逆に、非イオン化形態でのみ活性な基のイオン化が発生した場合にも、活性の阻害が発生する可能性があります。 この現象は主に強酸性または強アルカリ性の試薬を使用した場合に見られます。
阻害剤と基質は酵素への結合に相互に影響を与えませんが、阻害剤を含む酵素複合体は完全に不活性になります。 この場合、次の基本段階を想定できます。

v i / V = / [E] T
[E] T = [E] + + +
/ v i = (K s / V [S]) (1 + [I] / K I) + (1 / V) (1 + [I] / K I)
[I] = K I の場合、線の傾きと垂直軸との交点の縦座標は、1/v 0 と比較して 2 倍になります。
非競合的阻害剤は、例えば、ヘム酵素であるシトクロムオキシダーゼの触媒部位の一部である第二鉄にしっかりと結合するシアン化物です。 この酵素を遮断すると呼吸鎖が遮断され、細胞は死滅します。 非競合的酵素阻害剤には、重金属イオンおよびその有機化合物が含まれます。 したがって、水銀、鉛、カドミウム、ヒ素などの重金属イオンは非常に有毒です。 例えば、酵素の触媒部位に含まれるSH基をブロックします。
非競合的阻害剤はシアン化物で、ヘミン酵素であるシトクロムオキシダーゼの触媒部位の一部である第二鉄にしっかりと結合します。 この酵素を遮断すると呼吸鎖が遮断され、細胞は死滅します。 過剰な基質を使用して非競合的阻害剤の効果を除去することは(競合的阻害剤の効果と同様に)不可能ですが、阻害剤に結合する物質、つまり再活性化剤を使用する場合にのみ可能です。
非競合阻害剤は、農業害虫を防除するための薬理剤や有毒物質として、また軍事目的で使用されます。 医学では、水銀、ヒ素、ビスマスを含む薬剤が使用されます。これらの薬剤は、体の細胞や病原性細菌内の酵素を非競合的に阻害し、これらの薬剤の効果が決定されます。 中毒中、再活性化剤の助けを借りて、毒の結合または酵素阻害剤複合体からの毒の置換が可能です。 これらには、すべての SH 含有コンプレクソン (システイン、ジメルカプトプロパノール)、クエン酸、エチレンジアミン四酢酸などが含まれます。
非競合阻害
このタイプの阻害は、文献では反競争的とも呼ばれます。 または関連する阻害 , ただし、非競合的阻害という用語が最も広く使用されています。 このタイプの阻害の特徴は、阻害剤が酵素に結合できないが、酵素-基質複合体には結合することです。
非競合的阻害の場合、阻害剤を含む複合体は不活性になります。

v i / V = / [E]
[E] T = [E] + +
/ v i = K s / V[S] + (1 / V) (1 + [I] / K I)
基質阻害
基質阻害は、過剰な基質によって引き起こされる酵素反応の阻害です。 この阻害は、触媒変換を受けることができない酵素-基質複合体の形成によって起こります。ES 2 複合体は非生産的であり、酵素分子を不活性にします。 基質阻害は基質の過剰によって引き起こされるため、その濃度が低下すると緩和されます。
アロステリック阻害
アロステリック制御は、アロステリックエフェクターを結合するための制御中心を持つ、四次構造を持つ特別なグループの酵素にのみ特徴的です。 酵素の活性部位における基質の変換を阻害するネガティブエフェクターは、アロステリック阻害剤として作用します。 逆に、ポジティブ アロステリック エフェクターは酵素反応を促進するため、アロステリック アクチベーターとして分類されます。 酵素のアロステリックエフェクターは、ホルモン、金属イオン、補酵素のほか、さまざまな代謝産物であることがほとんどです。 まれに、酵素のアロステリックエフェクターの役割が基質分子によって果たされることもあります。
アロステリック阻害剤の酵素に対する作用機序は、活性中心の立体構造を変化させることです。 酵素反応の速度の低下は、K m の増加の結果、または基質の同じ飽和濃度、すなわち、基質の同じ飽和濃度での最大速度 V max の低下の結果のいずれかです。 酵素は部分的にアイドル状態です。
アロステリック酵素は、反応速度対基質濃度の特別な S 字型曲線を持つという点で他の酵素とは異なります。 この曲線はヘモグロビン酸素飽和度の曲線に似ており、サブユニットの活性中心が自律的に機能するのではなく、協力して機能することを示しています。 後続の各活性中心の基質に対する親和性は、前の中心の飽和度によって決まります。 中枢の協調的な働きは、アロステリックエフェクターによって決定されます。
アロステリック制御は、鎖内の最初の酵素の最終生成物による阻害の形で現れます。 最初の物質 (基質) の一連の変換後の最終生成物の構造は基質と類似していないため、最終生成物はアロステリック阻害剤 (エフェクター) としてのみ鎖の最初の酵素に作用します。 外部的には、このような制御はフィードバック機構による制御に似ており、最終生成物の収量を制御できます。最終生成物の収量が蓄積すると、鎖内の最初の酵素の働きが停止します。 たとえば、アスパラギン酸カルバモイルトランスフェラーゼ (ACTase) は、シチジン三リン酸 (CTP) の合成における 6 つの反応のうちの最初の反応を触媒します。 CTP は AKTase のアロステリック阻害剤です。 したがって、CTPが蓄積するとAKTaseが阻害され、さらにCTP合成が停止します。 ホルモンによる酵素のアロステリック制御が発見されました。 たとえば、エストロゲンは、グルタミン酸の脱アミノ化を触媒する酵素グルタミン酸デヒドロゲナーゼのアロステリック阻害剤です。
したがって、酵素反応の最も単純な反応速度式にもいくつかの速度パラメーターが含まれており、それぞれのパラメーターは反応が起こる温度と環境に依存します。
阻害剤は、酵素触媒作用の本質を理解することを可能にするだけでなく、特定の酵素の阻害剤を使用して特異的に停止できる個々の化学反応の役割を研究するためのユニークなツールでもあります。
3. 初期反応速度を測定するのに便利ないくつかの装置
酵素反応速度論の多くの問題は、初期反応速度 (v 0) の決定につながります。 この方法の主な利点は、蓄積する反応生成物がまだ反応を発揮する時間がないため、最初の時点で決定される v 0 の値が研究対象の酵素の活性を最も正確に表すことです。酵素に対する阻害効果に加えて、反応系は定常平衡状態にあります。
しかし、実験室での実践では、このような反応の進行を記録するために従来の分光測光法、滴定法、またはその他の技術を使用する場合、基質への酵素の添加、反応系の混合、設置などにより、最初からせいぜい 15 ~ 20 時間の時間が失われます。細胞など そして、この場合の接線は、tan ά 2 となる点に達するため、これは受け入れられません。< tg ά 1 . Не компенсируется потеря начального времени и при математической обработке таких кривых при записи выхода v 0 на максимальный уровень (V). Кроме того, протекание реакций без 一定の混合は、試薬の体積濃度の変動によりさらに複雑になります。
以下に提案する分光光度計や pH 計などの簡単な装置は、v 0 を決定する際に示された誤差の原因を大幅に減らすことができます。
3.1 分光光度計の装置
分光光度計デバイスは、ディスペンサー 1、回転テフロン フィラメント 2 (スターラー)、およびロック蓋 3 で構成されます。
ディスペンサーはマイクロピペットであり、その一端は針 4 を備え、もう一端は幅広 5 を備えた形状になっています(酵素がゴム製チップ 6 に入るのを防ぐため)。
スペクトルセル 7 を覆うテフロンカバー 3 には 2 つの穴があります。1 つはカバーの中央にあり、2 つ目 (9) はセル 7 の不透明な壁と光の間のギャップの中央の上にあります。ビーム 10. テフロンチューブ 11 (内径 1 -1.5 mm) 一端は穴 9 に固定され、もう一端はモーターローターの前の固定突起 12 に固定されています。 13. テフロン糸 2 がチューブに挿入されています (糸の厚さ 0.5 mm) -0.6mm)。 糸の一端はモーター13の回転ローターに固定され、第二端はキュベット7内に通され、(混合を促進するために)螺旋の形に成形される。 モーターを取り外してもネジの位置はロックカバー3で決まり、頻繁にキュベットを交換する作業に便利です。
動作原理。分光光度計7の石英キュベットは基板14(約1.5〜2.0ml)で満たされ、分光光度計の恒温キュベットホルダーに挿入され、回転テフロン糸2を備えた蓋3で閉じられ、基板14に浸漬される。そして、その後のすべての操作は分光光度計の光ビーム内で実行され、レコーダーに記録されます。
作業の開始時に、下地を混合し、レコーダーペンで均一な水平(または「ゼロ」)の線を書きます。 ディスペンサー(酵素付き)を穴 8 に挿入し(針は基質溶液 14 に浸されています)、先端 6 を素早く絞ることにより、酵素(通常約 0.03 ~ 0.05 ml)が基質に導入され、ディスペンサーが反応します。削除されました。 成分の混合は 2.5 ~ 3 秒で終了し、レコーダー ペンは時間に対する光学濃度 (ΔA) の曲線の偏差によって反応の開始を記録します。
この装置により、分析のために反応系からサンプルを採取することも可能になります。 システムに阻害剤と活性化剤を追加します。 反応の進行状況の記録を妨げることなく、反応条件を変更 (pH、イオン強度などを変更)。これは、たとえば、分割を研究する場合に非常に便利であることがわかります。 n-「酸性」ホスファターゼによるNPF、切断 n-NFFはpH 5.0(またはpH 6~7)で行われ、酵素活性は蓄積によって決定されます。 n-pH 9.5〜10.0のニトロフェノール酸イオン。
このような装置は、酵素などの分光光度滴定を行うのにも便利です。
3.2 pH計用装置
pH メーターのデバイスは、フロー電極 1 の改良された先端、セミミクロセル 2、ディスペンサー 3、および pH メーターをレコーダーに接続するための電子回路で構成されます。 さらに、このデバイスには、標準 pH メーター電極 (4)、セル ホルダー カバー (5)、恒温フロー チャンバー (6)、基質溶液 (7)、受動磁石 (8)、および能動磁石 ( 9)。
pH メーター (LPU-01) のフロー電極の標準チップを、飽和 KCl 溶液で前処理したアスベスト糸を充填したテフロン チューブ 1 (内径 1.3 ~ 1.5 mm) に置き換えます。 糸の充填密度は、チューブを通る KCl 溶液の流量が元の未修飾の電極の流量に近くなるように調整されます。 このチップの交換により、初期作業セルのサイズを 20 ~ 25 から 2 ml に縮小することができ、高価な生化学薬品の溶液を最小限の量 (1.5 ml) で使用できるようになります。
pH メーター (LPU-01) をレコーダーに接続するための電子回路は、電源 (DC 12 V バッテリー)、交流配線抵抗 R 1 (10 ~ 100 オーム) で構成され、電圧を 9 V に設定します。電圧計の読み取り値に応じた D809 ツェナー ダイオード、レコーダー スケール上の pH メーター読み取り値の「ゼロ」(基準点)の設定を調整する交流配線抵抗 R 2 (15 ~ 150 オーム)、および可変配線抵抗 R 3 (35 ~ 500 オーム)。レコーダーの pH スケール読み取り値の拡大 (増幅) スケールを調整します。 この回路は、電源電圧が 9 V を下回るまで確実に動作します。
動作原理。 1.5 ml の基質をセル (ガラスシリンダー 1.7x2.4 cm) に加え、セルをロック蓋 5 に固定します。撹拌 9 をオンにし、レコーダー ペンで偶数 (基本) 基準線を書き込みます。 ディスペンサーを使用して、酵素溶液 0.03 ml を基質に添加し、レコーダー ペンで pH 対時間 (t) 曲線の偏差によって反応の開始を記録します。
このようなデバイスはpH統計に代わるものではありませんが、pHメーターのスケールを拡張する可能性を考慮して、0.004〜0.005のpHの小さな変化を確実に記録することができます。
3.3 初速度の決定に便利なノモグラム定規
接線法で初速度を決定する際のかなりの複雑さは、単位時間 (Δt) あたりの試薬濃度の変化の比率 (Δ[S])、つまり 次の条件から式 v 0 (M/min)
v 0 = lim Δ[S] / Δt、t 0。
実際には、そのような手順は通常 3 つまたは 4 つの別々の操作で構成されます。つまり、反応進行曲線の最初のセクションに接線を引き、その後、記録された値 (光学濃度、回転角など) の単位数を 1 つ当たり計算します。一定の時間間隔をカウントし、これを単位時間に換算し、最後に 1 分間の試薬濃度の変化 (M/min) をレコーダーの読み取り値で再計算します。 提案された 2 種類のノモグラム定規を使用すると、この手順を簡素化できます。
長方形の定規。 v 0 は比 Δ[S]/Δt、つまり tg ά、ここで ά は時間軸 t に対する接線の傾斜角です。 同じ接線は、脚 [S] とそれに対応する直角三角形の斜辺でもあります。 v 0 が大きいほど、接線の傾きは急になります。 したがって、特定の時間間隔、たとえば 1 分に制限すると、脚 [S] の異なる値 (実際には v 0 の異なる値) を持つ一連の直角三角形が得られます。 両方の脚を校正する場合: 水平 - 時間単位 (1 分)、垂直 - 試薬濃度の変化単位 (ミリモル (mM) など) で、結果のセグメントを透明な素材 (プレキシガラス) で作られた適切なフォーマットに適用します。厚さ約 2 mm)を使用すると、初期反応速度を決定するための便利な定規を入手できます。 v 0 を決定する際の視差エラーを排除するために、すべての数字と線は定規の裏側に適用されます。
この場合、v 0 を決定する手順は 2 つの単純な操作に短縮されます。接線は反応速度曲線 t の最初のセクションに引かれます。 2 定規の水平脚 t のゼロ点を接線の始まりと組み合わせると、接線の継続部分が、M/min 単位の v 0 の値を決定する点で濃度スケール [S] と交差します (脚の水平位置をオンにします。追加の操作は必要ありません。
アーク定規。濃度スケールが特定の半径の円弧に沿ってプロットされている場合、v 0 を決定する手順は 1 つの操作に簡略化できます。
直線 (「基本」) 線 2 が透明な素材のプレートに適用され (すべての数字と線は定規の裏側にも適用されます)、この線のゼロ点 (t=0, min) から半径は脚の長さに等しい t=1 分 [ では、上から下に弧 [S] を描き、それに沿って試薬の濃度 (たとえば、mM 単位の基質) の変化のスケールがプロットされます。
記載されているタイプの定規、分光光度計用のデバイス、および pH メーターは、酵素の基質特異性を研究するときや分光光度滴定などの際に、反応の初速度 (v 0) を決定するために長年使用されてきました。
結論
この研究は、酵素によって触媒される化学反応の速度の多くの環境要因への依存性を研究する酵素学の分野を調査しました。 この科学の創始者は、一般的なメカニズムの理論を発表したミカエリスとメンテンであると正当に考えられています。 酵素反応に関して、彼らは酵素のすべての速度論的研究の基本原理となった方程式を導き出し、それは酵素の作用を定量的に説明するための出発点として機能します。 元のミカエリス・メンテン方程式は双曲線方程式です。 Lineweaver と Burke は、ミカエリス・メンテン方程式を変換し、V max の値を最も正確に決定できる直線のグラフを取得することで、反応速度論に貢献しました。
時間の経過とともに、実験条件下での酵素反応における酵素反応速度の変化は減少します。 速度の低下は、基質の濃度の低下、阻害効果を持つ可能性のある生成物の濃度の増加、溶液の pH の変化、温度の変化など、さまざまな要因によって発生する可能性があります。環境の変化が起こる可能性があります。 したがって、温度が 10℃上昇するごとに、反応速度は 2 倍またはそれ以下に増加します。 低温は酵素を可逆的に不活性化します。 酵素反応速度の pH 依存性は、酵素の活性中心の官能基の状態を示します。 各酵素は、pH の変化に対して異なる反応を示します。 化学反応は、さまざまな種類の阻害剤を作用させることで停止させることができます。 初期反応速度は、ノモグラム定規、分光光度計用デバイス、pH 計などのデバイスを使用して迅速かつ正確に決定できます。 これにより、研究対象の酵素の活性を最も正確に表現できるようになります。
これらはすべて、今日の医療現場で積極的に使用されています。
使用したソースのリスト
1. ベリャソワ N.A. 生化学と分子生物学。 - Mn.: ブックハウス、2004。 - 416 ページ、病気。
Keleti T. 酵素反応速度論の基礎: Trans。 英語から - M.: ミール、1990年。 -350ページ、病気。
3. クノーレ D.G. 生物化学:教科書。 化学、生物用。 そして蜂蜜 スペシャリスト。 大学 - 第 3 版、改訂版。 - M.: もっと高いです。 学校 2002. - 479 ページ: 病気。
4. クルピャネンコ V.I. 酵素反応を表現するためのベクトル法。 - M.: ナウカ、1990年。 - 144 p。
5. レニンジャー A. 生化学。 細胞の構造と機能の分子基盤:Trans. 英語から - M.: ミール、1974 年。
6. ストロエフE.A. 生物化学:医薬品の教科書。 研究所と薬局。 ファック。 ハニー。 研究所 - M.: 高等学校、1986 年。 - 479 ページ、病気。
セヴェリン E.S. 生化学。 A. - 第5版 - M.: GEOTAR - Media、2009 - 786 p.、病気。
酵素反応速度
酵素反応の速度は、単位時間当たりに変換される基質の量または形成される生成物の量によって測定されます。 速度は反応初期の曲線の接線の傾き角によって決まります。
米。 2 酵素反応の速度。
勾配が急であればあるほど、速度は速くなります。 通常、時間の経過とともに反応速度は低下しますが、これは主に基質濃度の低下が原因です。
酵素活性に影響を与える要因
F. の作用は、温度、環境反応 (pH)、酵素濃度、基質濃度、特異的活性化因子および非特異的または特異的阻害因子の存在など、多くの要因に依存します。
酵素濃度
基質濃度が高く、その他の要因が一定である場合、酵素反応の速度は酵素濃度に比例します。

米。 3 酵素反応速度の酵素濃度への依存性。
触媒作用は常に、酵素濃度が基質濃度よりもはるかに低い条件下で発生します。 したがって、酵素の濃度が増加すると、酵素反応の速度も増加します。
温度
酵素反応速度に対する温度の影響は、温度係数 Q 10 によって表すことができます。Q 10 = ((x + 10) °C での反応速度) / (x °C での反応速度)
0 ~ 40°C の間では、酵素反応の Q10 は 2 です。言い換えれば、温度が 10°C 上昇するごとに、酵素反応の速度は 2 倍になります。

米。 4 唾液アミラーゼなどの酵素の活性に対する温度の影響。
温度が上昇すると分子の運動が速くなり、反応する物質の分子同士が衝突しやすくなります。 その結果、両者の間で反応が起こる可能性が高まります。 最大の活性をもたらす温度を至適温度と呼びます。 このレベルを超えると、衝突頻度は増加しますが、酵素反応の速度は低下します。 これは、酵素の二次および三次構造の破壊、言い換えれば、酵素が変性を受けるという事実によって起こります。

米。 5 さまざまな温度での酵素反応の過程。
温度が氷点に近づくか氷点下になると、酵素は失活しますが、変性は起こりません。 温度が上昇すると、触媒活性が再び回復します。
乾燥状態のタンパク質は水和タンパク質(タンパク質ゲルまたは溶液の形態)よりもはるかにゆっくりと変性するため、乾燥状態でのリンの不活化は水分の存在下よりもはるかにゆっくりと起こります。 したがって、乾燥した細菌の胞子または乾燥した種子は、湿った状態の同じ胞子または種子よりもはるかに高い温度への加熱に耐えることができます。
基質濃度
所定の酵素濃度では、基質濃度が増加するにつれて酵素反応速度も増加します。

米。 6 酵素反応速度の基質濃度への依存性。
理論上の最大反応速度 V max に決して到達することはありませんが、基質濃度をさらに増加しても反応速度に目立った変化が生じなくなる時点が到来します。 これは、基質濃度が高い場合、リン分子の活性中心はいかなる瞬間においても実質的に飽和しているという事実によって説明されるべきである。 したがって、どれほど過剰な基質が利用可能であっても、それは、以前に形成された酵素-基質複合体が生成物と遊離酵素に解離した後でのみ酵素と結合することができるため、高い基質濃度では、酵素反応の速度は両方の要因によって制限されます。基質の濃度と酵素-基質複合体の解離に必要な時間。
一定の温度では、リンは狭い pH 範囲内で最も効果的に機能します。 最適な pH 値は、反応が最大速度で進行する値です。

米。 7 酵素活性の pH 依存性。
pH が高くても低くても、F. の活性は低下します。 pH の変化により、イオン化した酸性基と塩基性基の電荷が変化し、これによってリン分子の特定の形状が変化し、その結果、リン分子の形状が変化し、主にその活性中心の形状が変化します。 pH の変化が急激すぎると、F. が変性します。 特定のリンの最適 pH 特性は、その直接の細胞内環境の pH と常に一致するとは限りません。 これは、F. が置かれている環境が彼の活動をある程度調節していることを示唆しています。
酵素反応の速度論。 反応速度論では、反応の速度、メカニズム、および酵素や基質の濃度、温度、環境の pH、阻害剤や活性化剤の存在などの要因の影響を研究します。
一定の基質濃度では、反応速度は酵素濃度に正比例します。 酵素反応速度の基質濃度依存性のグラフは等辺双曲線の形をしています。
酵素反応速度の酵素 (a) および基質 (b) の濃度への依存性
酵素反応速度の基質濃度への依存性について説明します。 ミカエリス・メンテン方程式:

ここで、V は生化学反応の定常状態の速度です。 Vmax - 最大速度。 Km - ミカエリス定数。 [S] - 基質濃度。
基質濃度が低い場合、つまり [S]<< Кm, то [S] в знаменателе можно пренебречь.
それから 
したがって、基質濃度が低い場合、反応速度は基質濃度に正比例し、一次方程式で表されます。 これは、曲線 V = f[S] の最初の直線セクションに対応します (図 b)。
高い基質濃度 [S] >> Km では、Km を無視できる場合、ミカエリス・メンテン方程式は次の形式になります。 V=Vmax。

したがって、基質濃度が高い場合、反応速度は最大となり、0 次の方程式で表されます。 これは、横軸に平行な曲線 V =f [S] のセクションに対応します。
ミカエリス定数に数値的に匹敵する基質濃度では、反応速度は徐々に増加します。 これは、酵素反応のメカニズムに関する考えと非常に一致しています。

ここで、S は基質です。 E - 酵素; ES - 酵素と基質の複合体。 P - 製品; k1 は酵素-基質複合体の形成速度定数です。 k2 は、初期試薬の形成に伴う酵素-基質複合体の崩壊の速度定数です。 k3 は、生成物の形成に伴う酵素と基質の複合体の崩壊の速度定数です。
基質変換率生成物 (P) の形成に伴う反応速度は、酵素-基質複合体の濃度に比例します。 溶液中の基質濃度が低い場合、複合体 (ES) に結合していない遊離酵素分子 (E) が一定数存在します。 したがって、基質濃度が増加すると、複合体の濃度も増加し、したがって生成物の形成速度も増加します。 高い基質濃度では、すべての酵素分子が ES 複合体に結合します (酵素飽和現象)。したがって、基質濃度がさらに増加しても複合体の濃度は実質的に増加せず、生成物の形成速度は一定のままです。
したがって、酵素反応の最大速度の物理的意味が明らかになります。 Vmax は、酵素が完全に酵素-基質複合体として存在する場合の酵素の反応速度です。.
ミカエリス定数は、定常状態の速度が最大速度の半分に等しくなる基質濃度に数値的に対応します。 この定数は、酵素と基質の複合体の解離定数を特徴づけます。

ミカエリス定数の物理的意味それは、基質に対する酵素の親和性を特徴付けるという点でです。 k1 > (k2 + k3) の場合、Km は小さな値になります。つまり、 ES複合体の形成プロセスは、ES解離プロセスよりも優先されます。 したがって、Km 値が低いほど、基質に対する酵素の親和性が高くなります。 逆に、Km が非常に重要な場合は、(k2 + k3) > k1 となり、ES 解離プロセスが優勢になります。 この場合、酵素の基質に対する親和性は低くなります。
酵素阻害剤と酵素活性化剤 . 酵素阻害剤酵素の働きを低下させる物質と呼ばれるものです。 変性剤 (重金属塩、酸など) はいずれも非特異的酵素阻害剤です。
可逆的阻害剤- これらは酵素と非共有結合的に相互作用する化合物です。 不可逆的な阻害剤- これらは、活性中心の官能基に特異的に結合し、酵素と共有結合を形成する化合物です。
可逆的阻害は、競合的阻害と非競合的阻害に分けられます。 競合阻害これは、阻害剤と基質の間の構造的類似性を示唆しています。 阻害剤は酵素の活性中心で起こり、かなりの数の酵素分子がブロックされます。 競合阻害は、基質濃度を高めることで取り除くことができます。 この場合、基質は競合阻害剤を活性部位から移動させます。
可逆的な阻害が起こる可能性がある 非競争的基板との関係で。 この場合、阻害剤は酵素への結合部位をめぐって競合しません。 基質と阻害剤は異なる中心に結合するため、IE 複合体および三元 IES 複合体を形成することが可能になります。三元 IES 複合体は分解して生成物を放出しますが、その速度は ES 複合体よりも遅いです。
による 彼の行動の性質阻害剤は次のように分類されます。
- 特定の、
- 非特異的。
特異的阻害剤酵素の活性中心を共有結合で結び、作用範囲から外すことで酵素に効果を発揮します。
非特異的阻害酵素に対する変性剤の影響(重金属の塩、尿素など)が関係します。 この場合、タンパク質の四次構造および三次構造が破壊された結果、酵素の生物学的活性が失われます。
酵素活性化剤- これらは酵素反応の速度を高める物質です。 ほとんどの場合、金属イオン (Fe2+、Fe3+、Cu2+、Co2+、Mn2+、Mg2+ など) が活性剤として機能します。 金属酵素には金属が含まれています。 補因子、そして酵素活性化剤として作用します。 補因子は酵素のタンパク質部分にしっかりと結合できますが、活性化因子はアポ酵素から簡単に分離できます。 このような金属は触媒作用に必ず関与し、酵素の活性を決定します。 活性剤 触媒効果を高めるしかし、それらが存在しなくても酵素反応の進行は妨げられません。 一般に、金属補因子は基質の負に帯電した基と相互作用します。 可変価数の金属は、基質と酵素間の電子の交換に関与します。 さらに、それらは酵素の安定な遷移構造の形成に関与し、ES複合体のより迅速な形成に寄与します。
酵素活性の調節 。 代謝を調節する主なメカニズムの 1 つは、酵素活性の調節です。 一例は、アロステリック制御、つまり活性化因子と阻害因子による制御です。 代謝経路の最終生成物が調節酵素の阻害剤であることがよくあります。 このタイプの阻害はと呼ばれます 逆阻害、または負のフィードバックの原理に基づく阻害。
多くの酵素は不活性な酵素前駆体として生成され、適切なタイミングで部分的なタンパク質分解によって活性化されます。 部分的なタンパク質分解- 分子の一部の切断。これにより、タンパク質の三次構造が変化し、酵素の活性中心が形成されます。
一部のオリゴマー酵素は、次のような理由で活性が変化することがあります。 関連 - サブユニットの解離、彼らの作品に含まれています。
多くの酵素は、単純なタンパク質とリンタンパク質の 2 つの形態で存在します。 ある形態から別の形態への移行には、触媒活性の変化が伴います。
酵素反応の速度は次のものに依存します。 酵素の量、細胞内のこれは、その合成速度と崩壊速度の比によって決まります。 酵素反応の速度を制御するこの方法は、酵素活性を制御するよりも遅いプロセスです。
§ 12. 酵素反応の反応速度論
酵素反応の速度論は、酵素反応の速度とさまざまな要因への依存性に関する科学です。 酵素反応の速度は、特定の条件下での単位時間当たり、単位体積当たりの反応した基質または結果として生じる反応生成物の化学量によって決まります。
ここで、v は酵素反応の速度、 は基質または反応生成物の濃度の変化、t は時間です。
酵素反応の速度は酵素の性質に依存し、それが酵素の活性を決定します。 酵素活性が高いほど、反応速度は速くなります。 酵素活性は、酵素によって触媒される反応速度によって決まります。 酵素活性の測定は、酵素活性の 1 つの標準単位です。 酵素活性の 1 つの標準単位は、1 分間に 1 μmol の基質の変換を触媒する酵素の量です。
酵素反応中、酵素 (E) は基質 (S) と相互作用し、酵素 - 基質複合体が形成され、その後分解して酵素と反応生成物 (P) が放出されます。
酵素反応の速度は、基質と酵素の濃度、温度、環境の pH、酵素の活性を増減させるさまざまな調節物質の存在など、多くの要因によって決まります。
知ると面白いですね! 酵素は、さまざまな病気を診断するために医学で使用されています。 心筋梗塞が起こると、心筋の損傷と破壊により、血液中の酵素アスパラギン酸トランスアミナーゼとアラニンアミノトランスフェラーゼの含有量が急激に増加します。 それらの活動を検出することで、この病気を診断することが可能になります。
酵素反応速度に対する基質および酵素濃度の影響
酵素反応速度に対する基質濃度の影響を考えてみましょう (図 30)。 基質の濃度が低い場合、反応速度はその濃度に直接比例しますが、濃度が増加すると反応速度はよりゆっくりと増加し、基質の濃度が非常に高い場合、速度は実質的に濃度に依存せず、その濃度に達します。最大値(V max)。 このような基質濃度では、すべての酵素分子が酵素-基質複合体の一部となり、酵素の活性中心の完全な飽和が達成されます。そのため、この場合の反応速度は実質的に基質濃度に依存しません。
米。 30. 酵素反応の速度の基質濃度への依存性
基質濃度に対する酵素活性の依存性のグラフは、ミカエリス・メンテン方程式によって記述されます。この方程式は、酵素の反応速度論の研究に多大な貢献をした傑出した科学者 L. ミカエリスと M. メンテンに敬意を表してその名が付けられました。酵素反応、
ここで、v は酵素反応の速度です。 [S] – 基質濃度。 K M – ミカエリス定数。
ミカエリス定数の物理的意味を考えてみましょう。 v = 1/2 V max とすると、K M = [S] が得られます。 したがって、ミカエリス定数は、反応速度が最大値の半分になる基質濃度に等しくなります。
酵素反応の速度は酵素の濃度にも依存します (図 31)。 この依存関係は単純明快です。
米。 31. 酵素反応速度の酵素濃度依存性
酵素反応速度に対する温度の影響
酵素反応速度の温度依存性を図に示します。 32.
米。 32. 酵素反応速度の温度依存性。
低温(約 40 ~ 50 ℃まで)では、ヴァント ホフの法則に従って温度が 10 ℃上昇するごとに、化学反応速度が 2 ~ 4 倍増加します。 55~60℃以上の高温では熱変性により酵素の活性が急激に低下し、その結果として酵素反応速度の急激な低下が観察されます。 酵素の最大活性は、通常40~60℃の範囲で観察されます。酵素活性が最大となる温度を至適温度といいます。 好熱性微生物の酵素にとって最適な温度は、より高温の領域にあります。
酵素反応速度に対するpHの影響
酵素活性の pH 依存性を図に示します。 33.
米。 33. 酵素反応速度に対するpHの影響
pHのグラフは釣鐘型です。 酵素の活性が最大となるpH値をこう呼びます。 最適pH酵素。 さまざまな酵素の最適pH値は大きく異なります。
酵素反応の pH 依存性の性質は、この指標が以下に影響を与えるという事実によって決まります。
a) 触媒作用に関与するアミノ酸残基のイオン化、
b) 基板のイオン化、
c) 酵素とその活性中心の立体構造。
酵素阻害
酵素反応の速度は、と呼ばれる多くの化学物質によって低下する可能性があります。 阻害剤。 阻害剤の中には、シアン化物など人間にとって毒となるものもあれば、医薬品として使用されるものもあります。
阻害剤は主に 2 つのタイプに分類できます。 不可逆そして 可逆。 不可逆的阻害剤 (I) は酵素に結合して複合体を形成しますが、その複合体を解離して酵素活性を回復することは不可能です。
不可逆的な阻害剤の例は、フルオロリン酸ジイソプロピル (DFP) です。 DPP は、神経インパルスの伝達に重要な役割を果たす酵素アセチルコリンエステラーゼを阻害します。 この阻害剤は酵素の活性中心にあるセリンと相互作用し、それによって後者の活性をブロックします。 その結果、ニューロンの神経細胞のプロセスが神経インパルスを伝達する能力が損なわれます。 DPP は最初の神経ガスの 1 つです。 それに基づいて、人間や動物にとって比較的毒性のない多くの製品が作成されています。 殺虫剤 -昆虫にとって有毒な物質。
可逆的阻害剤は、不可逆的阻害剤とは異なり、特定の条件下で酵素から簡単に分離できます。 後者のアクティビティが復元されます。
可逆的な阻害剤には次のものがあります。 競争力そして 非競争的阻害剤。
競合阻害剤は基質の構造類似体であり、酵素の活性中心と相互作用し、基質の酵素へのアクセスをブロックします。 この場合、阻害剤は化学変化を受けず、可逆的に酵素に結合します。 EI複合体の解離後、酵素は基質と接触してそれを変換することも、阻害剤と接触することもできます(図34)。 基質と阻害剤の両方が活性部位のスペースをめぐって競合するため、この阻害は競合と呼ばれます。
米。 34. 競合阻害剤の作用機序。
競合阻害剤は医療で使用されます。 スルホンアミド薬は、以前は感染症と戦うために広く使用されていました。 構造的には次のものに近いです。 パラアミノ安息香酸(PABA)、多くの病原性細菌にとって必須の増殖因子。 PABA は葉酸の前駆体であり、いくつかの酵素の補因子として機能します。 スルホンアミド薬は、PABA から葉酸を合成する酵素の競合阻害剤として作用し、それによって病原性細菌の増殖と繁殖を阻害します。
非競合的阻害剤は構造的に基質と類似しておらず、EI の形成中に活性中心ではなく酵素の別の部位と相互作用します。 阻害剤と酵素との相互作用により、酵素の構造が変化します。 EI複合体の形成は可逆的であるため、その分解後、酵素は再び基質を攻撃できるようになります(図35)。
米。 35. 非競合阻害剤の作用機序
シアン化物 CN - 非競合阻害剤として作用する可能性があります。 補欠分子族の一部である金属イオンに結合し、これらの酵素の活性を阻害します。 シアン化物中毒は非常に危険です。 それらは致命的になる可能性があります。
アロステリック酵素
「アロステリック」という用語は、ギリシャ語のアロ(他のもの、ステレオ)のサイトに由来しています。 したがって、アロステリック酵素には、活性中心と呼ばれる別の中心があります。 アロステリックセンター(図36)。 酵素の活性を変化させることができる物質はアロステリックセンターと呼ばれます。 アロステリックエフェクター。 エフェクターは、ポジティブ - 酵素を活性化するもの、ネガティブ - 阻害するものです。 酵素活性を低下させます。 一部のアロステリック酵素は、2 つ以上のエフェクターの影響を受けることがあります。
米。 36. アロステリック酵素の構造。
多酵素系の制御
いくつかの酵素は協調して作用し、各酵素が代謝経路の特定の段階を触媒する多酵素系に結合します。
多酵素系では、一連の反応全体の速度を決定する酵素が存在します。 この酵素は通常アロステリックであり、代謝産物経路の最初に位置します。 さまざまな信号を受信することにより、触媒反応の速度を増減させることができ、それによってプロセス全体の速度を制御します。
酵素反応速度論では、反応する物質 (酵素、基質) の化学的性質とそれらの相互作用条件 (培地の pH、温度、濃度、活性化剤または阻害剤の存在) が酵素反応の速度に及ぼす影響を研究します。 酵素反応の速度 (u) は、単位時間あたりの基質の量の減少または反応生成物の増加によって測定されます。
基質濃度が低い場合、反応速度は
はその濃度に正比例します。 高い基質濃度では、酵素のすべての活性部位が基質によって占有されます ( 基質による酵素の飽和)、反応速度は最大となり、基質濃度 [S] に依存せず一定となり、酵素濃度に完全に依存します (図 19)。
KS – 酵素-基質複合体の解離定数 ES、平衡定数の逆数:
 .
.
K S 値が低いほど、基質に対する酵素の親和性が高くなります。
 |
| 米。 19. 一定の酵素濃度における酵素反応速度の基質濃度への依存性 |
基質の濃度と酵素反応速度の定量的な関係は次のように表されます。 ミカエリス・メンテン方程式:
 ,
,
u は反応速度、u max は酵素反応の最大速度です。
ブリッグスとホールデーンは、次のように方程式を改善しました。 ミカエリス定数 K m、実験的に決定されます。
ブリッグス・ホールデン方程式:
 ,
,
 .
.
ミカエリス定数は、酵素反応速度が最大値の半分になる基質濃度 (mol/l) に数値的に等しくなります (図 20)。 K m は基質に対する酵素の親和性を示します。その値が低いほど、親和性は大きくなります。
1 つの基質を含むほとんどの酵素反応の K m の実験値は、通常 10 -2 ~ 10 -5 M です。反応が可逆的である場合、酵素と直接反応の基質との相互作用は、異なる K m によって特徴付けられます。逆反応の基質のものから。
G. ラインウィーバーと D. バークはブリッグス-ハルデン方程式を変換し、次の直線方程式を取得しました。 y = ax + b (図21):
 .
.
Lineweaver-Burk 法では、より正確な結果が得られます。

米。 21. ミカエリス定数のグラフによる定義
ラインウィーバー・バーク法による
酵素の性質
酵素は多くの特性において従来の触媒とは異なります。
熱不安定性、または温度上昇に対する感受性(図22)。

米。 22. 酵素反応速度の温度依存性
ヴァント・ホフの法則によれば、45 ~ 50 °C を超えない温度では、温度が 10 °C 上昇すると、ほとんどの生化学反応の速度が 2 倍に増加します。 50 °C を超える温度では、反応速度が酵素タンパク質の熱変性の影響を受け、徐々に酵素タンパク質が完全に失活します。
酵素の触媒活性が最大になる温度を酵素温度といいます。 最適な温度。ほとんどの哺乳類の酵素にとって最適な温度は 37 ~ 40 °C です。 低温(0℃以下)では、酵素は原則として破壊されませんが、その活性はほぼゼロに低下します。
培地のpH値に対する酵素活性の依存性(図23)。
各酵素には、最大の活性を示す最適な pH 値があります。 最適pH動物組織における酵素の作用は、進化の過程で発達した生理学的pH値6.0〜8.0に対応する水素イオン濃度の狭い領域内にあります。 例外はペプシン - 1.5-2.5; アルギナーゼ – 9.5-10。
 |
| 米。 23. 酵素反応速度の培地のpH依存性 |
環境の pH の変化が酵素分子に及ぼす影響は、その活性基のイオン化の程度に影響を及ぼし、その結果、タンパク質の三次構造と活性中心の状態に影響を与えます。 pH はまた、補因子、基質、酵素-基質複合体、および反応生成物のイオン化も変化します。
特異性。酵素の作用の高い特異性は、基質と酵素の分子間の構造的および静電的な相補性と、反応の選択性を保証する活性中心の独特な構造組織によるものです。
絶対的な特異性 –単一の反応を触媒する酵素の能力。 例えば、ウレアーゼは尿素のNH 3 とCO 2 への加水分解反応を触媒し、アルギナーゼはアルギニンの加水分解を触媒します。
相対的(グループ)特異性 –特定のタイプの反応グループを触媒する酵素の能力。 たとえば、タンパク質およびペプチド分子のペプチド結合を加水分解する加水分解酵素ペプチダーゼと、脂肪分子のエステル結合を加水分解するリパーゼは、相対的な特異性を持っています。
立体化学的特異性空間異性体の 1 つだけの変換を触媒する酵素を持っています。 酵素フマラーゼは、ブテン二酸のトランス異性体であるフマル酸からリンゴ酸への変換を触媒し、シス異性体であるマレイン酸には作用しません。
酵素の作用の高い特異性により、考えられるすべての変換のうち特定の化学反応のみが確実に発生します。